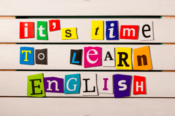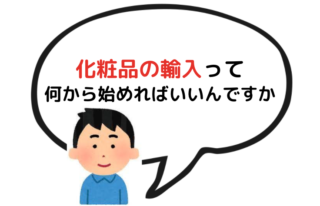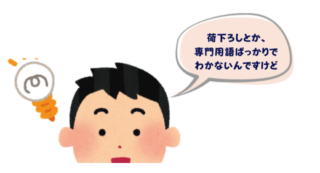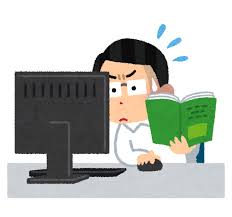【ネイティブの会話が聞き取れない】入れない理由と対策

英語を勉強していると必ずぶつかるこの問題。成長したぞと思って外国人だけの会話に参加したら、「早すぎて何を言っているかわからず、話しにはいれなかった」という経験あるのではないでしょうか。
勉強のさきが見えなくなったり、モヤモヤすることもあるかとおもいますが、この問題にぶつかったことは後退ではなく前進です。全く自信がなければそういった場所にはいかないでしょうし、「ネイティブだけだと早すぎて、自分はまだわからない」とわかったことがひとつの成長です。それを前提に、この記事では「ネイティブの会話にはいれない」問題がなぜ起こるのか、そしてどうしたらいいのかを紐解いていきます。
スポンサーリンク
なぜ、ネイティブの会話にはいれないのか

自身のさまざな経験、また生徒さんの相談を聞く中で、ざっくりわけて、ネイティブの会話には入れない理由は3パターンあることに気付きました。それは、
- ①会話にわからない単語・表現がでてきて、内容がわからなくなるパターン
- ②所々わかるが、話しを理解するのに必死でアウトプットができないパターン
- ③文化が違うので、そもそも話題を自分の知らないパターン
逆に話せないのに、入っていけちゃう「わからなくてもリアクションでなんとかなるパターン」なんかもあるのですがそれはまた別の機会に。ここでは、上記3つをパターン別に深掘りしていきます。
① 会話にわからない単語・表現がでてきて、内容がわからなくなるパターン

これは、そもそも自分が持っている語彙力や表現が足りていない場合があります。下記は君の名は(英語版)に出てきたですが、
- 「Sucks to be her(やだ~かわいそうに~)」なんて嫌味な表現も
- 「My memory is hazy. (記憶が曖昧で..)」Hazy(霞む)という言葉も、
知らなければ、考えてもわからないのです。
子供のとき大人同士の会話で「それなに?」と聞くことが多かったのと同じです。ですからこのパターンでは、本や映画で語彙やフレーズを増やしたり、わからない言葉が出てきたら「いまのどういう意味?」って聞いてみたり、とにもかくにも、「自分のなかの英語ストック」を増やすことが、キーになります。わかる言葉が増えていくと、アテがつくようになっていくので、大分会話が弾むようになっていくはずです。
スポンサーリンク
②所々わかるが、理解するのに必死でアウトプットができないパターン
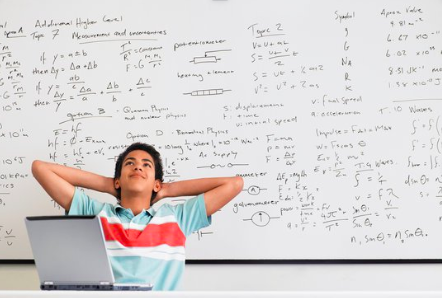
所々わかるということはつまり、「必死でこんな話か、こうかな」と考えるのにいっぱいいっぱいで、自分が話すことができない、もしくは自分が話す(アウトプット)するまでに話しが流れちゃうといった場合です。
このパターンは、
- 聴きながら話すことが苦手、もしくは
- スピードが速くなると追いつけない、
といった原因が考えられます。独学や、英語教室では自分に合わせたスピードで学習ができますが、ネイティブだらけの会話ではそういうわけにはいかないのです。これを克服ためには「早い英語に慣れる」こと、そして「それに自分が瞬時に反応する力」を鍛えることが有効です。ネイティブキャンプのカランや、シャドーイングは「反射的に英語で返す」練習ができるのでお勧めです。
③そもそも、話題が自分の知らないものパターン

イギリスで人気の映画の話題で盛り上がっていても、自分が知らないものであれば、盛り上がるのは物理的に難しくなりますし。育った環境が国レベルで違うと、「何を面白い」と思うかも違ったりします。これは日本人同士の会話でも同じこと。
なのでこの問題にぶつかったら、無理をせず「今日は入れなかったな~」と割り切る、交流会などでそれがずっと続くようなら別のグループに移動してもいいとおもいます。そしてさきをみて、出来る対策としては、いろんな人と話して、共通の話題(もしくは話の種)をできる限り増やすことです。
スポンサーリンク
「英語がスムーズに出てこない時」ってこんなとき

個人的には、思いっきり日本語をつかったあと、日本語脳(日本語で考えて英語に置換→アウトプット)になっているときはスムーズに英語が出てこないことが多いです。

直近の例ですが、相手が刀の形をした剣を持っていて、「刺さないで〜」と言いたいけど、出てこない。別に「刺す」の表現がわからなくても、「Don’t teasing me~ (いじめないで)」「Don’t kill me. (ころさないで~)」といった英語表現はたくさんあるのですが、
ひとつの訳にとらわれると「ダメだ出てこない」と空回り。日本語に囚われると堂々巡り。英語脳のタンクを増やしつつ、常に頭を柔軟にしておくことが重要かもしれません。
スポンサーリンク
対面会話はキャッチボール、複数会話はドッチボール

会話はよくキャッチボールに例えられますけれど、日本人が複数のネイティブの会話にはいっていくのはどっちかっていうとドッチボールに近いとおもいます。相手がこっちを狙って投げてくるキャッチボールとは違って、球がどの方向から降ってくるかわからず、ボールを取れなければアウトでコート外に出されてしまう。
はい、ということは、逆に起こりうるわけですね。アウトになって外に出ても、そこでボール(わかる会話)をキャッチして中に戻ることも可能。なので、わたし含めいろんなレベルの皆さんが、同じ課題で悩む事があると思うのですが当面の対策としては、そんなもんだ、と割り切って、わかるときにjump inするというのがいまの自分でできること、なのかなと思います。
スポンサーリンク
あとがきにかえて

というわけで、この記事では、ネイティブ同士の会話に入れない理由と対策をパターン別にご紹介しました。3年ほど前大スランプに陥ったときに、バイリンガルの先生に聞いたら、「それ英語力の問題じゃないのでは、もっと自分の存在をアピールしなよ」と思わぬ解答をもらったことがありました。黙って「うんうん」聞いている(ふりをしている)と、「ああ、この子は黙っていたいのかな」とおもって会話はどんどん進んでいくらしいのです。
それ以来会話でわからないことがあると、「それなに?」と、「なんていった?」と積極的に話しにはいっていくようにしました。確かに受動的だったとおもったのです。でも能動的に動くようになったら、自分自身の心も変わっていきました。どうせならば、楽しんで、いろいろチャレンジして少しずつ感覚が掴めていくのではないでしょうか。
スポンサーリンク