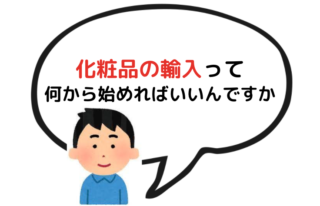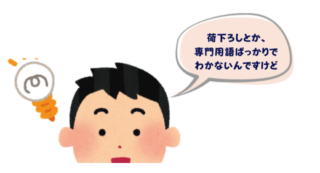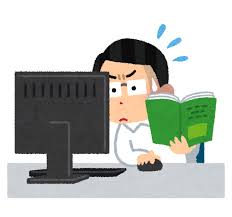【わかりやすい化粧品輸入】用意するべき書類や薬機法をかんたんに解説
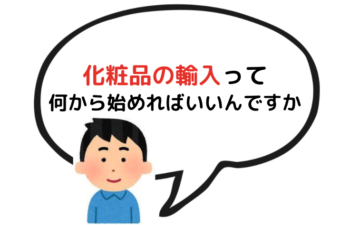
化粧品を輸入するには、通り抜けなくてはならない関門があります。今は簡単に個人輸入ができる時代ですが、「これ売れそうだから輸入してみよう」と軽い気持ちで動くと痛い目にあう可能性が高いことを忘れてはいけません。この記事では、損害を被らないためにも、わかりそうでわからない化粧品輸入のあれこれについてまとめました。
※ 最終的には、該当品の輸入地にある管轄税関、厚生労働省、都道府県の薬務課に問い合わせて判断してください
スポンサーリンク
Contents
化粧品輸入の流れ

こちらが、新規で化粧品を輸入する場合の簡単な流れとなります。
- サプライヤーと取引可否の交渉
- 取引可能であれば、サンプルの取り寄せ
- 輸入にあたり、成分等問題がないかを確認
- 問題がなければ、先方と契約締結
- 発注 (注文書/Purchase Order発行)
- 支払い (インボイスに基づいて送金、前払いか後払いかは契約次第)
- 商品の発送
- 日本での輸入通関
- 検品 (不良品があれば先方と相談)
- 納品
尚、これは販売目的での輸入を想定しています。
輸入に問題がないか、契約前に確認しよう

「これは良い商品だ、売れそうだ」と見込んで、最初から大量に仕入れるのは危険です。
契約前には、先方へ相談して必ず成分表を取り寄せるようにしましょう。というのも、海外と日本では化粧品配合成分の基準が異なるのです。海外で流通していても、日本では化粧品への配合が禁止されているものや配合の上限が設定されている場合があります。
輸入・販売しようとしている化粧品の成分表などをあらかじめ取り寄せ、”日本の化粧品基準に適合しているかどうか”確認しておきましょう。確認先は、厚生労働省、もしくは事務所がある都道府県の薬務課です。
- 厚生労働省 (化粧品・医薬部外品等ホームページ)
- 東京都福祉保健局 (薬務課) ※輸入事務所の所在地が東京の場合
役所へ確認するときのポイント

とはいっても、ざっくり「この化粧水なんですけど、輸入できますか?」と問い合わせても明確な返事はもらえません。またサンプルを取り寄せて現物を持っていったとしても
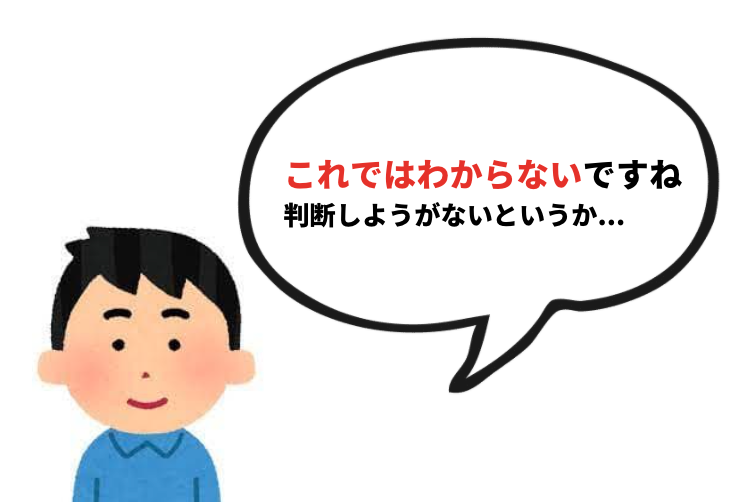
と返されることが殆どです。
役所に確認するときには、必ず成分表を含めた具体的な資料を提示するようにしましょう。
資料には、こういったポイントを含めると役所も判断しやすくなります。
- どういう商品であるか、
- 商品のコンセプト
- 使用方法
- 成分表
を記載したまとめ資料を作って、問題ないか否かを判断してもらう形となります。また質問する先として「厚生労働省」と「各都道府県の薬務課」という選択肢がありますが、輸入できるか否かを判断するのが厚労省で、のちに解説する薬機法関連を取りまとめているのが薬務課となります。
スポンサーリンク
化粧品輸入に必要な書類

さて、化粧品を輸入するにあたって、必ず突破しなければならないのが書類の壁です。まず、販売用か、個人での使用かでパターンが異なるのですが、このサイトを見ていらっしゃる方は恐らく日本での販売を考えていらっしゃるのではないでしょうか。この二つは分けて、解説していきたいと思います。
① 個人使用の場合

この場合は、通関時に下記書類が必要となります。
- インボイス
- パッキングリスト
- 該当化粧品の成分表
- 化粧品の説明書 (あれば良)
個人で使用する目的で輸入する場合は、特にむずかしい書類を準備する必要はありません。
普通と違うといえば「成分表」くらいでしょうか。成分表と説明書は必ずしも求められるわけではないのですが、「毒劇物ではないか」「ワシントン条約に違反している成分が入っていないか」を税関から聞かれた場合、「該当しないですよ」「入っていないですよ」と、輸入に問題がない旨をはっきりと明言するために用意しておいた方が良いものです。

また、日本の業者が依頼して、外国のメーカーから消費者に直接発送してもら場合なども基本的に同じです。
② 日本国内で販売する場合

輸入した化粧品を国内で販売する場合は、「薬機法」と呼ばれる法律が絡んできます。ということで、輸入時は、税関へ下記書類を提出する必要があります。
- インボイス
- パッキングリスト
- 該当化粧品の成分表 (あれば良)
- 化粧品製造販売許可証の写し
- 化粧品製造販売届書の写し
を提出する必要があります。
販売用に輸入する場合は、成分表以外に「化粧品製造販売許可証の写し」と「化粧品製造販売届書の写し」が必要になるのですね。この「薬機法 (旧薬事法)」と呼ばれるものがわかりにくいんですよね。どういうものなのか、次のパラグラフで具体的に解説していきたいとおもいます。
スポンサーリンク
薬機法とは
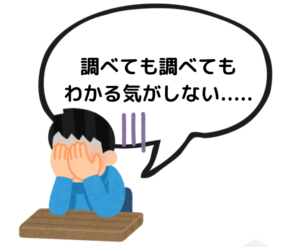
薬機法とは、その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。かんたんにいうと、輸入した化粧品を日本市場で販売 (流通) させる場合は、「薬機法」に準拠する必要があるということです。
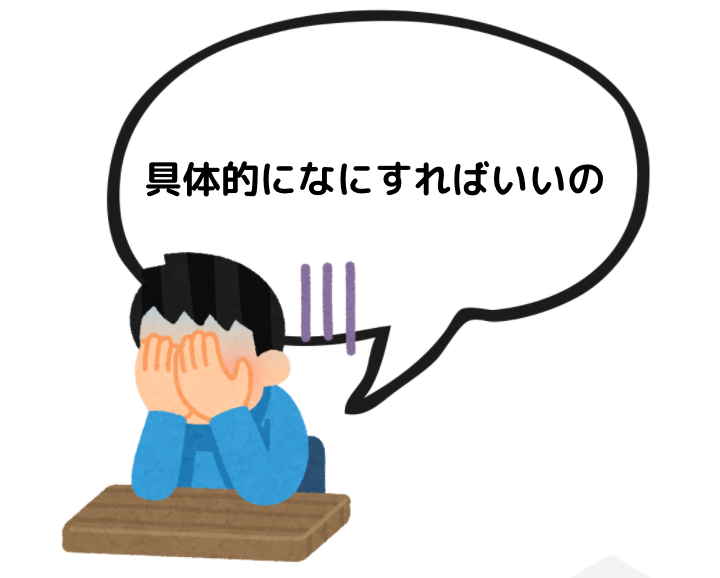
具体的には、
- 「化粧品外国製造販売 (製造) 業者届書」を提出 (提出先は(独)医薬品医療機器総合機関)
- 「化粧品製造販売業」「化粧品製造業」の許可を取得 (担当は各都道府県の薬務課)
をすればいいのです。
申請に必要な書類は、こちらの資料に詳しく説明がされています。いずれもすぐに通るものではないので、充分に資料を揃えてから申請にのぞむ必要があります。

また簡単に取れるものでもないので、これが難しい場合は輸入代行といって、すでに届出を出して許可をもらっている事業者にお願いして代わりに輸入してもらうという手もあります。いずれも輸入前に全ての届出を済ませておく必要があり、先方と契約をする際はこういった申請期間も見込んでスケジューリングするのが望ましいでしょう。
まとめ
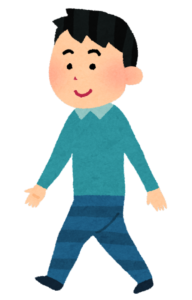
個人目的で輸入するためには、
- サプライヤーから成分表を取り寄せて、
- 厚労省か、都道府県の薬務課に輸入可否を確認
- 問題なければ発注して輸入
- 日本の業者が依頼して、外国のメーカーから消費者に直接発送してもら場合も同じ
販売目的で輸入する場合は、
- サプライヤーから成分表を取り寄せて、
- 厚労省か、都道府県の薬務課に輸入可否を確認
- 輸入が可能な旨確認が取れたら、薬機法で定められているものを準備 (※)
- (※)「化粧品外国製造販売 (製造) 業者届書」を提出 (提出先は(独)医薬品医療機器総合機関)
- (※)「化粧品製造販売業」「化粧品製造業」の許可を取得 (担当は各都道府県の薬務課)
このふたつが取得できたら、
- 発注して輸入
- 税関に薬機法に準拠している旨を申告して、通関 (具体的には上記書類の写しを提出)
- ふたつがむずかしいようであれば、すでに取得している業者に代行輸入をお願いする
ということでした。
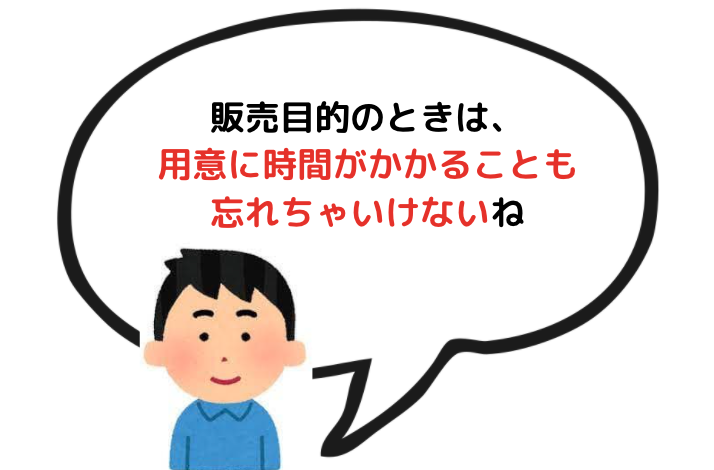
個人利用の場合は、成分に問題がなければ割と容易に輸入できるのですが、それを国内で販売するとなると膨大な事務処理が必要となるのですね。「なんとかなるさ」で進めると、いざ通関時に輸入の許可が降りず「積み戻し」になったり、「廃棄」となったり、膨大な費用が発生するだけでなく先方へも大きな迷惑をかけることにもなります。
わからなくなったら、必ず担当の役所に確認をとってください。ビジネスを長く続く良いものにするためにも、ぜひ慎重に進めていっていただければと思います。
関連記事
- 【海外取引の自力解決が危険な理由】大抵は何とかならずに大火傷!?
- 【DHL Eパケット】貨物が届かない、追跡情報がアップデートされない場合の対処法
- 【海外取引でのトラブルは超厄介】初心者が気をつけるべき3つのこと
- 【海外銀行への電話】HSBC口座が凍結しそうな時の対処法
- 【アジア工場との取引き】クオリティを担保するためには粘り強い交渉が必須
スポンサーリンク